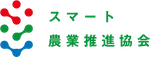【レポート】2020年2月_スマート農業勉強会

イベントレポート
新富町スマート農業勉強会
2020年2月19日(水)、宮崎県新富町にて「新富町スマート農業勉強会」が開催されました。3回目となる今回は、水耕栽培関連の新システムを開発・研究している2社が登壇。自社システムの紹介から現状の課題、今後の展望までわかりやすい説明に参加者は熱心に聞き入っていました。
アマノ株式会社

イノベーション開発センター
高橋 正 氏
「化石サンゴを使ったアルカリ培地での水耕栽培システムについて」
『アマノ株式会社』は国内初のタイムレコーダー開発企業。タイムレコーダーは国内シェア40%、コインパーキングのパーキングシステムでは国内で60%のシェアを誇ります。
同社は神奈川県相模原市での実証実験を経て、農業初心者でも美味しく作れる「化石サンゴ」を使ったアルカリ培地と養液の組み合わせによるトマトの水耕栽培システムを構築しています。
化石サンゴを使い培地をアルカリ性にするとトマトに適度な負荷がかかり、甘くて美味しいトマトができるそう。共に研究開発した神奈川県のベンチャー企業『株式会社プラントライフシステムズ』のAI灌水コントロール技術を使うことでpHやECの環境制御が容易に行え、新規就農者でも美味しいトマトを作ることができる、と高橋氏は話します。その理由を学術的観点から証明するため、東京大学と共に研究研究を進めているそうです。
同社のシステムを導入すると、毎朝7〜8時に栽培指示がAIから届きます。それに従って人間が圃場で灌水などの作業をします。「完全自動化はしないのか」との質問には、「第一には莫大なコストの問題があり、今のところ全自動ではありません。また農場に何がしかスタッフが足を運ぶことを考えると、人の手を必要とする部分があってもいいのでは。病気や異常の早期発見にも繋がります」という高橋氏の説明がありました。
現在の水耕栽培の主流は、ヤシ殻やロックウールを使用した培地。化石サンゴは海外から運搬するため1反で50〜60万円と初期導入コストは高くなりますが、20年間使っている農家がいること、また洗って再生可能であることを考えると、長期的には決してコストは高くないといいます。

▲質問をする参加者
また別の参加者から「具体的にはpHがどのくらいだと甘くなるか?」との質問があり、「品種によって違いはあるが、8〜10度くらい」と回答。pHが上がることで根からの病気にかかりにくくなった、というのも現状でわかっているメリットなのだとか。

▲参加者は食い入るように説明を聞き、質問のレベルも高い
「AIには、環境データだけじゃなく現場の植物データも入力するのか?」と高度な質問も。
「植物の成長度合いも計測したり、データとしては持っているが、現在のところ過去のデータと環境データのみでAIが制御している」と高橋氏が回答。「やはりコスト面とのバランスを考えるとそうならざるを得ない。80%美味しいトマトはできるが、篤農家に敵わない部分もある」など、次々に飛び交う質問に一つひとつ対応されていました。
グリーンリバーホールディングス株式会社

代表取締役
長瀬 勝義 氏
小面積・高収量な「縦型水耕栽培システム」と、再生可能エネルギーの利用例紹介
福岡市に本社を構える『グリーンリバーホールディングス株式会社』は、再生可能エネルギー事業・次世代農業事業を手掛ける企業。今回、新富町で紹介した同社のサービスは、「縦型水耕栽培システム」です。
土を使用せず、独自の培地で葉物野菜やハーブ類を栽培できます。C型のカバーでメディア(培地)を包み、その真ん中にフェルトを挟みます。そこを点滴のように養液が伝わり、植物に栄養を与える仕組みです。日当たりが良ければ家の壁面でも葉物が育てられるとあって、インテリアや壁面緑化などにも役立つシステムです。このシステムで実際に同社はバジルを栽培し、加工し、商品化までワンストップで行っています。

▲新富町の農業従事者にとって、とても興味深い内容となった勉強会の様子
このシステムはIoT化されているため、作業指示と遠隔操作、同社によるフォロー体制の充実で今まで農業に携わっていなかった人でも栽培が可能。装置は縦型のため省スペース、移動も可能なので場所を選ばない作業性の良さもメリットです。機械のコントロールは同社が行い、地域の特性によっては今後レストランやホテルなどが店産店消で利用することも可能だとか。
また、同社が手掛ける再生可能エネルギーの利活用例の紹介もありました。太陽光をはじめ地熱発電や風力発電、ゴミ処理場から出る排熱を利用した施設園芸事業など、自治体と協力して進めているモデル事業も増えているそうです。

どちらも、個人経営で導入するには大きな費用がかかります。縦型水耕栽培システムに関しては、「今後、企画していきたいのがレンタルサービス。定額制でサービスを提供していけたら、と考えています」と長瀬氏。また小型のユニットを今年3月には発売予定で、「興味のある方は、ぜひこちらから段階的にトライしていただけたら」と興味深い情報も飛び出しました。

参加者たちからは、「飲食店等に導入できないか」「ハウスに地熱を引いたらコストはどのくらいか」、また「環境制御は業界で統一させることはないのか」など、踏み込んだ質問が出されました。
3回目のスマート農業勉強会を終えて

▲勉強会に参加されていた黒木新悟さんは、川南町のミニトマト農家
新富町と同じ児湯郡内の川南町で、ミニトマト栽培をしている黒木新悟さんは、「サンゴ培地にはとても興味がわきました。今は作業に関して判断できるのが自分だけなので、IoTを活用して自分以外のスタッフも全員同じことができるようになるといいですね」と、スマート農業への期待を持っているようです。

▲現役大学生も参加
また、参加者の中には明治大学農学部に在学中の大学生2人も。「新富町に来ていたので、今後を考えて参加してみました。これからの農業は本当におもしろいと思います」と、目を輝かせて話してくれました。
今回の勉強会では、登壇者のプレゼンテーションに対し積極的に質問を投げかける参加者の姿勢が印象的でした。
勉強会を含め新富町の農業を取り巻く環境に触れた、今回の登壇者のお二人にとっても、大きな手応えと刺激を感じた時間だったようです。

「開発側と現場の農家さんがタッグを組み、現場に寄り添った開発が進められているし、農家さんはそれを使いこなしている。農家さんたちのレベルの高さに驚きました」と長瀬氏。
高橋氏も、「技術や知識をシェアするマインドを持った農家さんが多くいらっしゃるし、とても柔軟にスマート農業を受け入れる土壌ができている町。スタートアップを支援する体制も整った先進的な町ですね」と感銘を受けている様子でした。

来たる3月18日(水)、今期最後の新富町スマート農業勉強会を開催予定となっています。