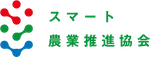求む、農業新時代へーベンチャー精神から学ぶスマート農業会議ーゲスト:日本経済新聞社の吉田忠則氏
宮崎県新富町に設立されているスマート農業推進協会の公開オンライン勉強会が開催されました。スマート農業推進協会は、全国から農業に関する知見を集結し、地方からスマート農業を推進している団体です。
日本は農業人口の高齢化と人口減少により農家の後継者や担い手不足が深刻化しています。今後生産者が半減していくという予想がある中、日本の農業が稼げる産業に進化するために注目されているのがスマート農業です。
今回は、日本経済新聞社で「食と農」に関するテーマを幅広く取材しているジャーナリスト、吉田忠則氏をゲストに迎え、農業新時代に求められているベンチャー精神についてお話していただきました。
内容
- 農業で起業しよう(地方)
- 農業で起業しよう(都市近郊)
- 会社員の経験は強みになる
- 新たに注目される有機農業
- カイゼンとスマート農業
<スマート農業推進協会 オンライン勉強会>
開催日時:2021年8月10日 (火)
テーマ:未来型農業経営のヒントー楽しく稼げるスマート農業会議
現場の実践者らの生の声が聴ける人気講座がオンライン開催
【講師紹介】※敬称略
吉田忠則
日本経済新聞社編集委員

1964年千葉県生まれ。1989年京都大学文学部を卒業し、日経新聞に入社。流通、郵政、農政、保険、首相官邸などの担当を経て、2003年から4年間、北京に駐在した。03年「生保予定利率下げ問題の一連の報道」で新聞協会賞を受賞。07年から編集委員。食と農の取材では、農家から農業法人、農協、植物工場、飲食店、スーパー、食品メーカーまで幅広くカバーする。徹底した現場取材をもとに、農業の構造変化をつかむことを目指す。日経電子版と日経MJで連載「食の進化論」、マイナビ農業で連載「農業経営のヒント」、雑誌「経営実務」で連載「農業の可能性を探る」を執筆している。農業関連の著書は「農は甦る」(12年)「コメをやめる勇気」(15年)「農業崩壊」(18年)、「逆転の農業」(20年)。https://www.nikkei.com/journalists/19041000
求む、農業新時代へ ベンチャー精神

農業取材を始めたときの疑問と答え
吉田さんは、約10年前から農業に関する取材を続けています。当初、吉田さんは日本の農業にはなぜ暗い話が多いのか、その根本原因は何なのかと疑問に感じていました。
そのなかで吉田さんが行き着いた答えが、農業を取り巻く構造的な難しさ。
現在の日本では食べるものに困ることはなく、世界中からおいしい食材が入ってきます。
豊かな食生活のなかで、食品は常に余裕のある状況にあり、余っているのです。そのため、強い価格下方圧力がかかり、農業が収益を上げにくい原因となっているのではと言います。
今回は、そのような状況の中で日本の農業を盛り上げている人を紹介していただきました。
農業で起業しよう(地方)
地方就農の1つ目の事例は、担い手不足に悩んでいた埼玉で、新規就農した若手経営者を紹介していただきました。この農家では、日本の農地を守るというミッションを掲げ、ヨーロッパや米国を参考に粗放型経営を取り入れていることが特徴です。また、この経営者は学生時代にベンチャー企業を起業した経験があり、経営についてよく理解していることも強みとなっています。
地方就農の2つ目の事例は、徹底的なブランド化を行う米農家。企業で会社員をしていた経験を基に、どうしたら高く売れるかを考えていました。その結果、辿り着いたのが新規顧客開拓。三越・伊勢丹・西武などのデパートや高級和食店、JAL国際線のファースト・ビジネスクラスなどを相手に、1kg5,000円の高価格で米を販売し成功しています。美味しく食べる方法を徹底リサーチしたことで、米のブランド化に成功しました。
農業で起業しよう(都市近郊)
都市近郊での就農事例も紹介していただきました。
まずは、日本にない野菜で産地化を行ったケースです。生産家・行政・シェフ・卸がタッグを組んだことで、良い循環を生み出しました。
また、兼業農家のあり方にも新しい動きが出ています。多品目の野菜と32種類のじゃがいもを直売と産直サイトで販売している方の夫は会社員。これまで家族経営ばかりだった農業に、新しい波が来ていると感じます。
新しい兼業農家の価値を生み出すことは、これからの日本にとって重要と言えるでしょう。
会社員の経験は強みになる
ここまでの事例を見ても明らかですが「農家にとって会社員の経験は、非常に重要な価値となる」と吉田さんは改めて強調します。
会社員を経験したあと就農した方は、一年で数度の収穫経験を得られる九条ねぎを栽培することで、農家としての栽培経験不足を補いました。また、需要の変化を察知し、新規市場を開拓。栽培農家が周囲にある関西ではなく、ラーメンブームとなっていた関東へ九条ねぎを売り込むことにしたのです。東京で栽培されているのは青ネギが多く、関西のネギは珍しかったこともあり、重宝されました。このときは、ラーメン店などに直接売り込んでおり、営業経験が活きたというわけです。
新たに注目される有機農業
環境配慮型農業への転換は、長期的な国際トレンドです。そのなかで「有機農業がビジネスとして成立するための鍵だ」と吉田さんは話します。
素材の価格暴落があるなかで、有機農法の導入で価格をコントロールするメリットを、有機こんにゃくの事例とともに説明いただきました。有機農業によって、大手の食品メーカーが参入できないプラスαの価値を生み出すことができます。
有機農業は、ビジネスとして儲かるためのチャンスになっているのです。
カイゼンとスマート農業
最後に、スマート農業のトレンドについてもお話いただきました。ポイントとなるのは、最先端の技術ではなく、現場目線の技術開発が必要とされているということです。
田んぼの水を管理するのに、シシオドシの仕組みを応用した技術を導入した事例や、農協への出荷報告をスマホのアプリで簡略化した事例を挙げ、シンプルな仕組みや他の分野では当たり前の取り組みでも、農業の現場では重宝されると教えていただきました。
ここからわかるのは、農業でも「カイゼン活動」は有効だということです。どの事例でも、ビジネスマンとしての発想が活きていました。
パネルディスカッション
イベントの最後には、鹿児島堀口製茶有限会社の代表取締役副社長であり、スマート農業推進協会 広報拡散部長としても活躍されている堀口大輔氏をお迎えし、パネルディスカッションが行われました。
【パネラー】(敬称略)
-
- 堀口大輔
スマート農業推進協会 広報拡散部長
鹿児島堀口製茶有限会社 代表取締役副社長

1982年9月、鹿児島県有明町(現志布志市)生まれ。明治大学経営学部卒業後、静岡県の伊藤園に入社。生産本部農業技術部の新産地育成事業で産地指導から仕入れにつなぐ仕事に4年間従事した後、2010年4月帰郷し、父親の堀口泰久氏が社長を務める鹿児島堀口製茶/和香園に入社。
取締役として主に生産体制の改善などに取り組み、2018年7月、同社代表取締役副社長および和香園代表取締役社長に就任。日本茶インストラクターの資格を持つ。茶畑面積は300ha(うち自社管理茶園120ha)。R1年度及びR2年度 農林水産省 スマート農業加速化実証プロジェクトに取り組む。
スマート農業推進協会 広報拡散部長
九州アイランドワーク 広報宣伝拡散部長
テラスマイル 広報部長
ハチドリ電力 広報宣伝部長(九州顧問)
高橋:農業の「経営」としての感覚は、日本に昔からあったという話を聞きました。
吉田:昔は、結といって農家が緩やかに繋がっていて、有機的に結びついて集落の中で田んぼの作業を進めていました。これは、大規模農業で各自が自分の役割を理解しているのと似ていますし、この形が農業の真髄です。しかし、戦後の農地開放で、小規模農家が一斉に兼業化していったことで忘れられてしまいました。
堀口:現在、ほとんどの農家が家族経営の個人事業主です。そこで私達は、大枠のなかで農業法人がいて、取引先については各農家が一方向に向きつつも、それぞれが各自農業を行うという形を考えています。結という農業システムと非常に似ていると感じました。
高橋:ビジネス経験からの農業では、会社員時代の知識が重要なのでしょうか?
吉田:知識というよりは発想が重要でしょう。作ったものを売るのではなく、マーケットがあるものを作るという発想の転換です。
また、農業では、ただ栽培を行うだけではなく、段取りづくりも重要となります。その部分にビジネス経験が活かされていることが多いですね。ビジネスマンは客観的なデータなどの視点で考えるので、それが強みとなっています。
ースマート農業の話に移っていきます。
高橋:スマート農業というと、大規模でロボットが全自動で農業を行うイメージを持つ方が多くいらっしゃいます。しかし、実際の現場で必要とされているのは、少し収量が上がり、手が回らない部分を助けてくれるような存在です。
AGRISTでは、ベンチャーだからこその柔軟性で、現場で実際に役に立つスマート農業を行っていきたいと考えています。これまでのスマート農業だと、ロボットのスペックが高すぎる部分があったのは事実ですが、少しずつ変わろうとしているのではないでしょうか。
吉田:ロボットだけの性能を極めるのではなくハウス自体の改良を行う必要がある、と考え方そのものが変わっていると感じています。
高橋:まさにその通りで、たとえばAGRISTでは、どういう圃場でロボットが効率的に動けるのか、分析しながら開発しています。AGRISTや堀口さんのように、農家とロボット開発との距離が近いのは強みです。
堀口:補助金が欲しいからロボットが欲しいでは、実際に使えるスマート農業にはなりません。ロボットと農業のミスマッチとなってしまいます。農家・開発者・行政が同じ目的を共有していくことが重要です。
吉田:堀口さんへ聞いてみたいのですが、お茶の品評はオンラインでは難しいものですか?
堀口:新型コロナウイルスの感染拡大で、県外の業者が鹿児島県内の市場に顔を出せず、うまく問屋さんとコミュニケーションが取れなかったことはありました。しかし、鹿児島ではお茶の数値化に積極的に取り組んでいます。
もちろん、香りなど実際に現物を見ないと難しい部分もあるので、どこまでを数値化に任せ、どの部分を人の手で確認するかは今後の課題です。AIの深層学習モデルを活用しようとしている動きもあります。
吉田:スマート農業は栽培現場だけでなく、サプライチェーンも巻き込んだ全体的なものですね。
高橋:未来型農業経営に関する話を最後にしたいと思います。環境に配慮した農業のはじめの一歩とは、どこになるでしょうか?
吉田:正直なところ、環境問題は個々の経営者ができる範疇を超えた大きな問題だと感じます。政治や政策で考えるべき問題とも言えるでしょう。ただし、環境調和に関するルール整備が進むなかでは、それを踏まえた上でビジネスとしてどのように競争力を高めていくのか、という観点が重要になると考えます。