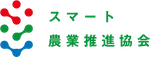【イベントレポート】第3回 儲かるスマート農業サミット@東京「農業とITの未来を語る」
宮崎県児湯郡新富町に、地域商社があることをご存知だろうか?農業で世界を変えようと「食と農のシリコンバレー」構想を進め、昨年末には国の地方創生優良事例にも選出された。それが、一般財団法人こゆ地域づくり推進機構(略称:こゆ財団)だ。
もともとは、財政難を背景にスピードまち経営を実践するため、2017年4月に、宮崎県児湯郡新富町が旧観光協会を法人化して設立された。こゆ財団の「稼いで、町に再投資する」ビジネスモデルは、1粒1,000円以上する高付加価値のライチに代表される特産品開発と、農家とベンチャー企業の協業など人材育成の好循環を促し、ふるさと納税寄附額を4億円から19億円へ成長させるなど「稼げる地域農家のモデル構築」を進めている。
さらに、こゆ財団は今年8月に新たな挑戦を始めた。「新富アグリバレー」プロジェクトをスタートするのだ。農家の所得向上や人材育成に挑む地域商社と自治体、農家、AI・IoT・アグリテックベンチャーが協働し実行する。
今、宮崎県新富町が熱い。
そんな新富町の立役者である齋藤潤一氏、スーパー公務員の岡本啓二氏、地元アグリテック農家の猪俣太一氏、ゲストには、テレビで話題の食べチョク秋元氏、東京大学大学院の海津准教授を迎えたイベントが、2019年8月30日に東京都千代田区内神田で開催された。会場には都内の農業ベンチャーや起業検討者が集まった。
多様性をはぐくんできたまち、新富町

齋藤:新富町の農業の魅力とは?
猪俣:新富町はフルーツや野菜や米、牛、鶏肉など生産されていて、生きていくのには困らない町です。それぞれの農家がつくっているものが違い、少数の農家にそれぞれに独自のつくり方があり、つくり方がばらばらで今までは統制が取れていない面もありました。今はITを導入して、共通の目標でみんなで一丸となっていこうという流れがでてきています。町全体でIT化に向けた流れが進んできていると感じますね。
齋藤:向いている方向が一緒だと強いですね。それに年間でフルーツが食べられるのは魅力です。フルーツが「安くて旨い!」と空港で爆買いして帰っていかれる方も多いですね。
岡本:新富町って太平洋沿岸部で、一年中ぽかぽかしてのどかな雰囲気です。住んでいる方もギスギスしていなくて、新しいことを始めるときにも「やってみよっかー」と前向きに取り組んでくださる特徴がありますね。ボトムアップでやるのは意外と潰されるイメージがありますが、新富町ではそれを受け入れてくれる寛容な環境があります。歴史的には2つの勢力に挟まれて、どちらかに柔軟につきながらやってきた背景もあり、多様性に向いていたというのもあると思います。
秋元:新富町には一度伺いました。個人的に、特に期待を感じたのはスピード感でしたね。できて三年目で結果がでてきていますし、他の自治体の地方創生事業と比較しても圧倒的なスピード感を感じました。人材育成の部分で、若者が集まっているのも役場との連携が上手く取れているのもあると思います。
ロボットの仕事は人間の作業や判断を「アシスト」すること
齋藤:スマートアグリについて伺います。海津先生はロボットだけじゃなくて、ドローンの事業開発もなさっていますよね?
海津:スマート農業は、幅が広いので「できること」「できないこと」がぼんやりしている側面もあります。ある人はこれができるといっても、他の人はできないといったりすることはありますね。大風呂敷を広げているところは問題としてあります。産学の学の立場の私は特に気をつけて見ないといけないところだと思っています。
農業とテクノロジーにスマートアグリは関わりがあります。私は特にロボットで難しさを感じています。工学部の人が農業に取り組んだらロボットはすぐできるんじゃないか? と思われる方も多いかと思いますが、それは簡単にはできないんですね。
なぜかというと、一つは作物の種類が多いこと。人と同じモノをつくるとそれが陳腐化してしまって、価格が下がってしまいます。例えばもやしは完全スマートアグリで、種を入れて水を入れてぽんとできます。ですが、その代わりにみんながやって、農家が儲かったかというとどんどん価格が叩き合いにあって、結局1パック17円みたいな価格設定になって儲からない。多種多様な作物に対応する必要性がありますが、それだと高コスト化してしまうので、高付加価値なものを楽につくれるように、ロボットが人間の作業や判断をアシストして、最終的には人間がやる農業が求められているのではないかと思います。
齋藤:仮に農業の全行程をロボットが行うようになると、「自分がつくらなくてもいいや」となるんですか?良い作物を安く提供しているという、社会的な価値があると思うのですが。
猪俣:農家にはプライドがあります。人と同じようなことはやりたくないという農家は一定数いらっしゃいます。いくら収益が上がっても人と同じやり方は真似しないという方もいます。

※新富町でキュウリの生産に情熱を傾ける猪俣氏。
齋藤:ロボットが人と違ってできないことは「共感」だと言われていますね。もはや「観光」としての農業と「生産」としての農業は分けるフェーズに来ているのだと言われています。アニメ「ドラゴンボール」にでてくる仙豆のような完全栄養フードがでてきてしまうと、それで十分という方もでてくると思います。
高付加価値な農業の鍵は「ストーリー」
齋藤:食べチョクさんは、農家の想いも含めた販売をされていますが、例えば全部機械で生産された野菜は売れると思いますか?
秋元:これから機械化が進んでいき、ストーリーの重要性が増すと思います。私は農業が二極化すると考えていて、効率的につくって安く買えるものと、高付加価値があってそこにストーリーのあるものにわかれると思います。

※新富町を訪れたことのある秋元氏。滞在時は地元農家の声に耳を傾けて回った。
私がやっている食べチョクというサービスは後者をやっています。結局、人が買う意味や、食べる時の楽しさをアップさせるポイントは背景にあるストーリーだと思います。今はオーガニックのモノだけを取り扱っていますが、生産者のこだわったストーリーのあるモノを販売していきたいですね。ただこだわりという表現は曖昧なもので、一般の人からするとわかりにくさがあります。将来的には自社基準を決めてオーガニック以外にもこだわったモノを販売していきたいと思います。
海津:世の中にはいろいろな価値があると思いますが、私はストーリー派です。農業は単価として高いモノではないので、ストーリーを伝えて適度な価格で楽しんで買っていただくことに意味があると思っています。例えば、山の中でおじいさんがつくっている野菜など、よりストーリーを持たせる食べ物が必要になると思います。
従来だと有機野菜は人が苦労すればするほど価値があるとされていましたが、そこをテクノロジーが解決します。害虫が多く発生する時期には、テクノロジーが湿度や水やりを管理する。そういったことをきめ細かくテクノロジーで対応するのが大切だと感じています。
齋藤:農業で販路は大事と言われていますが、どういうところが新しいんですか?
秋元:大事なのは、想いを貫くのと同時に正しく市場環境を把握し、スピード感ある事業展開をしていくことです。食べチョクのような産直のビジネスモデルは10年くらい前からあって、やっていることは新しくないんです。ただ産直のビジネスは消費者からすると利便性が低くなりがちで、生産者集めにも時間がかかる。事業としてスケールしづらいという課題がありました。
AmazonやOisixなどネットの小売サービスはたくさんあります。つまり「野菜を買うサービス」というと、消費者にはさまざまな選択肢があって目が肥えてるんです。
そんな競争が激しい中で、ビジネスとして勝っていかなければいけない。そのために想いだけでなく、スピード感も意識しています。目の肥えた消費者の方に、農家さんの利益も考えながらいかに価値を提供できるかを一番にしています。
質疑応答では、「ブランディングがメジャー化すると差別化をどうするか?」「日本で高効率に農業を進めには?」「海外進出で大事なポイントとは?」など高付加価値な農産物を提供し続けるために必要な戦略について質問が続いた。

※こゆ財団が手がけたライチのブランディングについて視察者に説明する岡本氏。
従来の倍の収入を得ることを目指す新富町
齋藤:海外勢との対峙はどうすべきでしょうか?
海津:ワインは海外からたくさん入ってくるといいと思います。美味しい海外ワインが市場に出るようになると、消費者の方がワインって「美味しいね」と魅力に気づくと思うんです。そこから、舌を肥やして日本のワインのすごさを知ることができると思います。
齋藤:新規の参入について教えていただけますか?
秋元:新規就農の段階ではこだわった農法を選ぶ方が多いんですが、やってみると売れない現状もあります。つくるだけの生産になると楽しさがなくなって辞めてしまう方も多いですね。食べチョクでは、場を提供して、農家さんが自分で梱包して送っています。自分らしさを出している方はどんどん売り上げが上がっていますし、そこを面倒だと思う方は厳しい場合もあります。新規就農で熱意のある方は食べチョクと相性が良く、利用される方が多いですね。
齋藤:効率化の先には何を思っていますか?
猪俣:オランダでは1回の投資が20億円前後と日本の100倍近くあります。日本では、田んぼの所有面積が狭く、拡大しようと思っても多数の農家への承諾が必要になります。日本の田んぼは一つ一つの距離があり、オランダの大規模密集地とは違います。日本の農業従事者の数は減っていくと予想されますが、アグリテックによって残った従事者が従来の倍の収入を得ることを新富町では目指しています。
齋藤:最後に一言ずつお願いします。
岡本:農業イベントは三回目なんですが、盛り上がりを感じています。農業は多様性と変化の可能性があるので、話がつきないのかなと思います。まだ誰も見たことがないアグリバレーをここ新富町で実現していきます。ぜひ新富町で一緒に進んでいきたい方がいらっしゃいましたらお声かけ下さい。
海津:農業ロボットで研究を始めて30年、やっと波が来たと思っています。お困りごとがあれば、私にご連絡いただいて一緒に方法を考えていきましょう。
猪俣:ぼくたち農家は、仕事中は外に出られないので、こゆ財団ができたことで外の方と関われました。今日のように東京に来て興味を持って聞いてくださる方にお会いすると、ぼくたちには刺激になります。是非また呼んでください!
秋元:私たちの会社は4年以内に上場したいと思って事業をやっています。農業の業界はやれていないことがたくさんあって、課題が多いからこそ、伸びしろがあり、楽しくてしょうがないと思っています。興味がある方が集まっているのは業界にとってもポジティブだと思っているので、いろんな方を巻き込みながらカタチにしていけたらと思っています。
会場では、新富町の梨や野菜が振る舞われた。参加者からの質問が絶え間なく続き、参加者同士の交流も盛んに行われた。